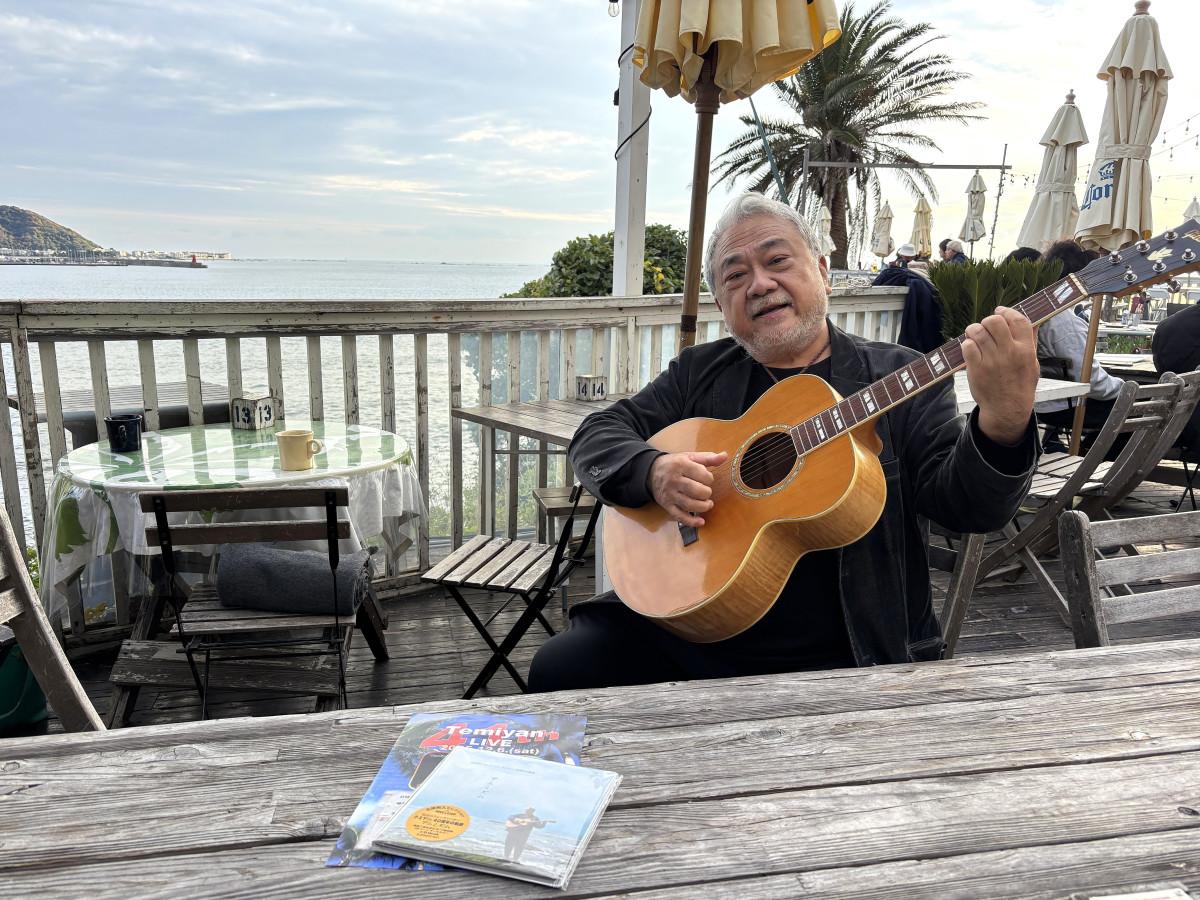逗子小学校でリサイクル体感授業 使用済みプラスチック教具が定規やカラビナに

逗子小学校の5年生が2月15日、「湘南貿易」(横浜市)のエコ事業部による特別授業でプラスチックリサイクルについて学んだ。
プラスチックリサイクル装置の説明をする「湘南貿易」の山本直さん。熱心に聞き入る児童たち
1月から15時間かけて5年生が学ぶ「個性を可能性に」授業の一環。児童たちは、靴、服、海、食など6つの中から好きなテーマを選び、3月8日の発表に向けて課題をまとめる。
この日、エコ事業部の山本直さんらの授業を受けた15人は、学校教材に使われるプラスチックのリサイクル課題に取り組んでいる。不要になった学校教材を事前に集め、教材販売を手掛ける「高山商会」を通じて「湘南貿易」に届けた。同社ではその教材を破砕してプラスチックをリサイクルするインジェクション装置とともに教室に持参した。
山本さんはゴミとなるプラスチックにはさまざまな種類があり、それを洗浄して種類別に分別することで質のいい別の製品に生まれ変わる、種類によって溶ける温度が違うことなどを説明した。
授業後半では、分別したプラスチックがどうやって形を変えていくかを体感するためにインジェクション装置に破砕した教材を入れて溶かし、児童がハンドルを回した。力いっぱい回すとクリーム状になったプラスチックが絞り出された。プラスチックは定規やカラビナ、ボタンなどに成型する型に流し込み、1~2分で固まった。
生まれ変わった物を手にした児童は「家では部屋ごとに分別できるゴミ箱があってプラスチックを分けているが、色も分けてリサイクルできれば色のきれいな物に変わると思った」「アルファベットの型があればいい。リサイクルは大切」などとプラスチックのリサイクルに関心を寄せていた。
山本さんは「プラスチックによって私たちの生活は恩恵も受けている。使い終えた後も、洗って分別すれば、ゴミで終わらない。ゴミとして海に流れる量を減らすことで、海の環境の破壊につながることもない。海が身近な逗子の子どもたちにリサイクルの工程が授業で見える化できれば」と力を込める。
5年生担任の高司智也教諭は「授業を通じて、知識だけでなく行動につなげてもらえたら」と期待を寄せる。